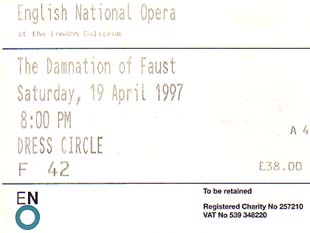《ジーザス・クライスト・スーパースター》終演後、ロイヤル・オペラ・ハウス(ROH)に寄ってみる。
この日の演目はバレエ《ロミオとジュリエット》(プロコフィエフ作曲)。
吉田都さんが出演するようで、並んでいる列には日本人も多く見られた。
それからピカデリーのジャパンセンター(本屋さん・日本人いっぱい)で、
朝日新聞、週刊ポスト(これが一番新しい週刊誌だかった から (^_^; )、文芸春秋(明日の飛行機用)を買って、£12(2400円)。
レスタースクエアまで行って、カフェで新聞を読む。
トップ記事は動燃解体とか。
ペルーの人質事件は未だ未解決。
その後、猿岩石のゴールとなったトラファルガー広場(イングリッシュ・ナショナル・オペラ /ENO の近く)を目指す。
広場に面したセント・マーティン・イン・ザ・フィールド教会では、6:30PMからバロックコンサートがあって、人が並んでいた。
10分でも聴いていこうかとも思ったが、ここでは2年前に室内楽コンサートを聴いたことがあるから、今回は止めておいた。
 |
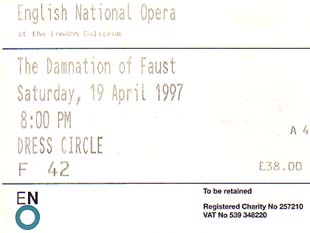 |
| コリシアム劇場 |
チケット |
風が強く寒かったので、早めにENOのあるコリシアム劇場に入る。
プログラムを買ったが、内容は分からないので、暇つぶしにロビーで週刊ポストを読んでいたが、おかしかったかな
(^_^;?
周りの人は皆プログラムを読んでいたな。
コリシアム劇場のエントランスロビーはROHよりもずっと立派。
ただ、驚いたことに、クロークが無かった。
地元の人もコートや荷物はひざの上に置いていた。
劇場内部は大変大きい空間で、4階までの座席が馬蹄型になっている。
壁の彫刻も立派で、建て替えの話があるそうだが、とんでもないことだ。
しかし、椅子はちょっとすり切れていたね。
ROHとの違いは、観客が普段着だということ。
僕もネクタイをせずに済ませてしまった。
この気楽な雰囲気は好きだな。
それから英語上演だということ。
日本ではROHより格下に考えられていると思うが(まあ実際そうなのかも知れないけれど)、上演のレベルは非常に高く本格的。
今までに、まだ3演目しか見ていないけれど (^_^;。
1997年4月19日(土)19:00
CONDUCTOR:MARK ELDER
DIRECTOR:DAVID ALDEN
FAUST A PHILOSOPHER:BONAVENTURA BOTTONE
MEPHISTOPHELES:WILLARD WHITE
MARGUERITE:LOUISE WINTER
BRANDER:GRAEME DANBY
ゲーテが《ファウスト》を書いたゲーテハウスは、数日前にフランクフルトで訪れたばかり。
ベルリオーズ作曲の《ファウストの劫罰》は、初めて見るオペラ。
というより、今回の予定が分かってからあわててショルティのCD(一番安かった)を買って2回通して聴いただけのオペラ。
そのような僕に、このような抽象的な演出は荷が重かった。
訳が分からない (^_^;。
DAVID ALDEN 演出のこのプロダクションは4月7日初演の新演出。
途中休憩はなく、2時間15分通しの上演。
舞台には真ん中を頂点とする三角形の大きい壁がある。
ここがファウストの書斎みたいだ。
《ハンガリー行進曲》の間、ファウストはたくさん積まれた本を、左の壁から右の壁に移している。
メフィストフェレスは、たしか紫のスーツを着て影のように現れる。
この人は黒人で、それがなかなか有効な場面かと思った。
やがて、中央が大きく開き、酔っぱらった学生たちが現れる。
やっとこれで話が分かるようになったかと思ったんだが、学生のリーダー・ブランデルは坊主頭の肥満体で半ズボンをはいていた (@_@)。
それから後は、何と言ったらいいのやら‥‥ (^_^;
『精霊の踊り』では舞台下手から、巨大な人形が現れ、ゆっくりと上手に向かって歩く (@_@)。
どれくらい巨大かというと、首から上は舞台からはみ出して見えないんだわね。
これがマルグリートの幻影だったようだ (^_^;。
『鬼火のメヌエット』では、ピエロや、ジャグラーたちが次々と現れる。
頭がたくさんある人物や、銀粉ヌード (^_^) も出てきた。
ここまでやってもらえば、さすがにこれが夢の世界か精神異常の世界だということは分かる。
そのうちに、拘禁衣を着た人たちが現れたから、たぶん精神病院なんだろうな、あれは。
で、訳の分からないまま終わってしまった (^_^;。
しかし、DAVID ALDEN の演出には、ボンの《パルシファル》(ギュンター・クレーマー)や フランクフルトの《フィデリオ》(クリストフ・マルターラー)に感じたような不快感はない。
とても舞台がきれいだし、不必要だと思われるものは無かった。
何と言ったらいいか、『演出家の意図を考えなくては』と思わせる演出ではあった。
また機会があったら、ALDEN 演出の舞台を見てみたいものだ。
もう少し、よく知っている演目でね (^_^;。
前のページへ 旅行記の最初へ ホームページへ 次のページへ
|